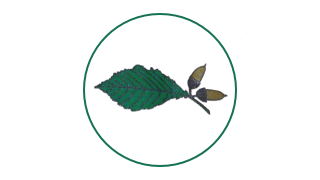[平成20年(2008)06月30日発行会報第21号から]
◆ はじめに 会長 勝田政吾
当会では、森づくりの諸課題に応じた5つの分科会をつくり、会員各位の参加によって、それぞれ企画してもらって幹事会で討議し年間作業計画に折り込むことにしています。自然が相手の作業が多いために、時期がずらせないもの(植樹や農作業)を中心に実施計画を組んで行かねばならないという制約もあります。また今年度からは、年次総会のご挨拶でも申しましたように、森づくりの方向性についても考えていこうと思います。
そうしたことを踏まえて分科会担当幹事に抱負を含めて今年度やりたいことを書いていただきました。
活動は会員全員参加が本筋ですから、どうぞ皆様には積極的にご意見をお寄せ下さり、奮って活動にご参加下さるようお願いします。
● 森づくり分科会( 動植物調査分科会) 勝田佳代子
多摩美の森は周囲の雑木林とのつながりを考えて、植樹については多摩丘陵の潜在自然植生つまり土地本来の樹種を植えていくことにより、私たちの区の健康の森とし
ての特色が出せると考えています。
手入れについては、ふれあいの森に続いている西側の雑木林とかなり茂ってきた北側の緩衝林、その手前の疎林を作るために植樹した所もそれぞれ手入れが必要です。そのために、雑木林の手入れについて専門家による勉強会をしたいと思っています。
また、広場のシンボルツリーのエノキは蝶の幼虫のためにもその木のためにも、根元をもっと大切にしたいと思います。
動植物調査分科会としては、秋に今年度2回目の自然観察会を予定しています。
●畑の管理分科会 中谷一郎

子供たちとサトイモの植付け 6 月15 日
本年度の畑の作付けは、上の「小さな畠」に小麦・大麦・ビール麦を栽培し、6 月には収穫、刈取り後、その畑を耕し、サツマイモ・サトイモの植付けを計画していましたが、ほぼ予定どおりに実施できました。
6月7 日(土)に大麦の刈取り、はざかけ(麦の物干し乾燥)、11 日(水)に畑の耕耘、サツマイモの植付け(べにあずま300 本)を行ないました。15 日(日)にはサトイモの植付けをし、さらに、下の「お楽しみの谷」隣の小麦の刈取り、たばね、はざかけも完了することができました。それは15 日には、うれしいことに、会員の親子と、サイクリングでこの森に見えた親子、遊歩道散策の親子が参加され、会員を含めて大勢で協力し、朝9時から昼を忘れ2 時頃まで働いたお陰です。
初めて参加されて、「楽しかった。これからも来たい」と早速会員になられた親子もおられました。
今後9 月の西生田小学校の体験学習に向けてソバの種まきをします。また麦の乾燥後脱穀作業が待っており、世界的に高騰している小麦が昨年同様25kg 以上も穫れて、「多摩美の森産小麦粉」として植樹祭・収穫祭のお土産用、バームクーヘン用に利用できるようにと、サトイモ・サツマイモの 豊作とともに期待しています。
若い会員の親子の方々が継続して来られ るよう、意見を積極的に採り入れる交流会 を2 ヶ月に1 回ぐらい開けないか、食事会 を含め検討したいと思いますので、どしど しご意見をください。
●施設工作分科会 伊丹伸行
施設工作分科会は本年度、①「多摩美の 森の家」の外周に砂利を敷くこと、②藤棚 の下のテーブルの補修等を計画しています。 ①は、「森の家」は雨が降ると周辺の泥 が跳ね上がり、せっかくの新しい外壁が泥 により汚れてしまいます。そこで周辺に溝 を掘り、砂利を敷くものです。②は、藤棚 の下に設けられたテーブルは、角材を並べ て作った丈夫で、自然の温もりのあるもの ですが、一部に腐りが出てきた所がありま すので、腐った角材3、4本、および周り の切り株の椅子の一部を更新するものです。
●広報分科会 木村信夫
本紙「麻生多摩美の森だより」21 号から 24 号まで4回の発行と、年次報告書の作成 を予定しているほか、各種イベントへの参 加、タウン誌等への情報提供などを精力的 に行い、さらなる会員の獲得に努めたいと 考えています。また総会でも提案がありま したが、会員以外にも開放された教養講座、 観察会などの企画に向けて、広報活動を充実させるべく検討中です。また、試作段階で止まっているホームページは、上記のよ うな対外的な働きかけや交流の広がりにあわせて運用段階に入ることが課題です。
■児童の体験学習支援 長澤

西生田小3 年生 そばの学習 07 年9 月
いまの子ども達は毎日、大変忙しい日程 をこなしています。そのため、野外に出て、 なおかつ緑に触れる活動はほとんどないと いっていいのではないでしょうか。 麻生区市民健康の森は、立地条件に恵ま れ、野外体験学習に活用されやすい里山で す。これまで当会では、小学生を対象に各 種の体験学習の場を提供し指導に当たって きましたが、児童たちはどうのように受け とめているのだろうか。 お礼の便りを見てみると、「そば処 櫟」 でのプロのそば打ち見学では、予想もしな かった道具を使った力強く真剣な作業に感 動し、自分もそば打ち職人になりたいという児童がいます。麦やそばの学習では、わ れわれの講義を真剣に吸収して、忘れられない体験として家庭で得意気に報告してい るといいます。
自然に触れ合う学習(ネイチャーゲーム、 樹木の二酸化炭素吸収量測定環境学習)で は、樹木や緑の大切さが改めて分かり、機 会があればもっと体験学習をしたいという 希望がたくさんありました。 私たち自身、児童たちが楽しく学び感動 する姿に触れると、苦労が喜びとなり、明 日からの活動のやりがいにつながります。 今年も、五感で自然に触れて喜びと感動が 得られ、豊かな感性が養えるような体験を 目指して、樹木、草花、作物や季節などあ らゆる自然を活用して、児童(小学3年、5年生)の体験学習を応援する計画です。皆 様のご協力をお願いします。